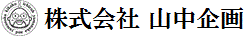「昭和ギャグベスト100選やっぱり笑いは「昭和」が面白い」
リリース記念特設ページ
ごあいさつ
この度、山中企画から初のオリジナルコンテンツ電子書籍「昭和ギャグベスト100選やっぱり笑いは「昭和」が面白い」が発売されました。
そこでこのページでは、山中伊知郎の過去の取材ノートから、「昭和ギャグの偉人たちへの取材記録」を公開していきます。
本のチラ見せではなく、WEBページだけの完全オリジナルコンテンツです。面白いと思えたなら、電子書籍も面白いと思えるはず。電子書籍(kindle)500円です。
第10回 ゆーとぴあ・城後光義に訊く 2015-03-10
「ゆーとぴあ」といえば、両腕を横に振っての「よろしくネ」と、口にくわえたゴムヒモを思い切り伸ばして最後は顔面直撃するゴムパッチンで、昭和50年代のお笑い界を席巻した名物コンビ。「よろしくネ」は、平成18年公開の映画『トリック劇場版2』にも登場し、若者たちにも親しみやすい昭和ギャグの一つとなっている。
その「ゆーとぴあ」のリーダー格であった「ホープ」こと城後光義さんは、今もリポーターとしてテレビに登場するとともに、ライブ活動などによって、後進のお笑い芸人たちをバックアップし続けている。
「こういう活動も始めたんですよ」
とインタビュー当時、見せていただいた週刊誌のグラビアには、城後さんが中心になって始めた「お笑い職業安定所」なるグループの写真記事が見開き2ページにわたって掲載されていた。何十年もやっていてもなかなか芽が出ない芸人たちを集めて、みんなで大爆発しようじゃないか、というユニットだ。
「まァ、それにしても、お笑いの世界も、昔に比べて、平和になったともいえるし、面白味がなくなったともいえますね」
と語りだす城後さんだが、彼が業界に入った昭和40年代は、まだまだお笑いの楽屋といえば、一種の「無法地帯」だったらしい。
「もう、背中に刺青入れてる芸人もいたし、刑務所からつい先だって出てきたって人とか、元はバナナのたたき売りだったっていう人とか、いろんな人がいましたね。キャバレーなんかじゃ、客から面白くないとグラスが飛んでくるし、お笑い芸人ていっても、みんなナメられちゃいけない、と身構えてる。お陰で人相が悪い人ばっかりでしたよ」
そんな中、あの「コントレオナルド」のレオナルド熊に弟子入りした城後さんは、主に全国各地のストリップ劇場を回る修業時代を送った。
「酒、オンナ、バクチ・・・・、人通り人間をダメにするものを、その間にみんなマスターしちゃうわけです。でもね、最近のお笑い学校育ちの連中と比べると、人生の深みっていうか、独特の味があったねェ。だいたい、芸人以外、とてもつとまりそうにないハンパな連中ばっかりだったから」
やがて、満を持して「ゆーとぴあ」を結成したのが昭和53年。しかし、そこから大きく飛躍しようとした時に巻き起こったのがMANZAIブームだった。
「漫才はお客さんの正面を向いてどんどん前に行くでしょ。その点、ボクらコントはどうしても横向きになっちゃうからインパクトが弱い。それに、テレビのネタが昔より短くなって、3分から5分くらいになった時代だったんで、最初の自己紹介のところから、強烈な印象を残さなくてはいけない、と考えたんですよ」
決めポーズもいくつかの変遷をたどり、やがて今の両腕を横に振るものに固定した。最初は、「何だ、それは」と客に唖然とされたが、浸透していくに従って、もう登場してこのフレーズを言うだけで、ドッと笑いが起こるようになっていったとか。
ゴムパッチン誕生の方は、赤坂のコルドンブルーという高級ショーパブに出演した時のことだ。そこは外国人客の多い店で、普通のネタをやってもてんで受けない。やるなら動きのあるギャグでなくては、といくつか試しにやってみたら、ゴムをのばしてパチーンと顔面に直撃するのが一番受ける。それなら、そのゴムの長さをできるだけ長くしようとやっていくうちに、あのゴムパッチン芸が完成していった。
「ボクが今でも仕事があるのは、あの「よろしくネ」とゴムパッチンのお陰。ただ、「よろしくネ」さえやれば、努力しないでも笑いが取れるでしょ。お金はどんどん入るし、モテまくるし。CMも来たし、武道館でライブまでやりましたし。もうこれでいいや、ってなっちゃった。ボクの堕落はあそこから始まったのかな」ごくあっさりした口調でそう語れてしまうあたりが、「昭和芸人の味」なのかもしれない。
第9回 田村隆に訊く 2015-02-05
「ゲバゲバ90分」「8時だよ! 全員集合」「みごろ!食べごろ!笑いごろ!」など、昭和を代表するお笑いバラエティに放送作家として関わりつづけた田村隆さん。ことにドリフとの関係は、昭和30年代、ジャズ喫茶で、あのいかりや長介と出会って以来の付き合い、というのだからハンパな関係ではない。
当然、数多くの昭和ギャグ誕生に瞬間にも立ち会っているわけで、ぜひそのあたりの話を伺いたくて、以前、インタビューに伺った。
まず最初に出たのが、「ゲバゲバ90分」の最大のヒットギャグ「あっと驚く、タメゴロー」についてだった。
「もともとは、あの一発モノ、いわゆるアイキャッチで一瞬出てくるシーンに、勝新太郎さんに出ていただくはずだったんです。勝さんに座頭市やってもらって、斬りまくってもらった上で「おもしれんですかい」とか何か一言いってもらう。本人のOKもとれてたのが、急にダメになっちゃった」
どうも、勝自身が躊躇したらしい。もし笑いの番組でそれやっちゃうと、いざ映画やテレビで座頭市やったら、笑いが来てしまうのではないか、と。
もっともな話で、急きょ、代役になったのが、やはり芸能界の重鎮であるハナ肇。「タメゴロー」については、恐らく,ハナ自身がつい放った言葉を、「それ、いい」になって採用されたらしい。ただ、あのヒッピー風衣装は、ちょうど昭和40年代半ば、ヒッピー、サイケが流行していた時代でもあり、スタッフの話し合いで、ぜひあれでいこうとなったとか。
とはいえ、田村さんといえば、まず浮かぶのがドリフ。その代表的なヒットギャグのエピソードを語ってもらおう。
「じゃ、「カトちゃんペッ」からいきますか。あれはね、実は『全員集合』よりもっと前、『ホイホイ・ミュージックスクール』っていう番組がはじまりなんです」
この『ホイホイ・ミュージックスクール』は昭和37年スタートの元祖シロート・スカウト番組であり、その後の『スター誕生』などの先駆的役割を果たしたもの。その中で一分の音楽コントがあり、まだ新人だった加藤茶も登場するチャンスを得た。だが、どうもキャラクターが薄いので、考えたあげく、鼻の下に指をくっつけて「ペッ! て感じにヒゲでもつけましょうか」と本人からの申し出があったらしい。あ、それいけるよ、となって「カトちゃんペッ」が生まれたらしい。
そして、もう一つの加藤茶の代表的なギャグである「ちょっとだけヨ」。これは、もともと加藤がかつて、川崎のストリップ劇場で照明のアルバイトをしていた話から始まる。客が踊り子さんに「もっと見せろよ」といい、踊り子さんが「ちょっとだけよ」と返すシーンがしばしばあったのを忘れずに、加藤は日常会話の中でしていたらしい。
それが、ある回、忠臣蔵のコントがあり、で浅野匠の内匠頭が切腹するシーンで、加藤がその内匠頭を演じた時のこと。「あ、裃脱いでく時に、あのストリップの「ちょっとだけよ」ってフレーズ、入れたらいんじゃない」となったのだ。
ちなみに、加藤、ストリップ劇場ではとんでもないミスをやらかしてクビになった。踊り子さんがパッとマタを開いた途端に暗転にしなければいけないのを、うっかり逆に思いっきり明転にして、踊り子さんを怒らせてしまったのだ。
「その踊り子のバックに流れていたのが『タブー』だったらしいですよ。」
そう、「ちょっとだけヨ」には欠かせない、あの曲だ。
加藤のヒットギャグといえば、他にも「ウンコチンチン」「1,2,3,4やったぜ、カトちゃん」「いかりやに、怒られた」など、いろいろある。
「強烈だったのが「ウンコチンチン」でしょう。単なる加藤さんの思いつきフレーズで、意味なんてない。語呂がおかしいだけ。それにテレビ番組でウンコとチンチンなんて、使っちゃいけないはずでしょ。もちろん抗議の電話も殺到しましたよ。そしたら番組プロデューサーが、「こんなに反応があるなら毎週やろう」って喜んじゃった」
『全員集合』は下ネタはOK。ただし、面白くなくてはいけない、とのルールがあった。
だから、「象さん」の替え歌で「象さん、象さん、おハナが長いのよ。そーよ、チンチンもなーがいのよ」と加藤が歌い、抗議電話が殺到した時も、「ウケてる」とプロデューサーもいかりやもニンマリだったらしい。
志村けんについていえば、「東村山音頭」という鉱脈を見つけるまでに、しばらく手間がかかったという。
「荒井注さんが抜けて、翌週からいきなり『志村、行け』ですからね。本人はキツかったと思いますよ」
名物コーナーの少年少女合唱隊では、様々な分野の音楽が使われた。その中で民謡を歌う週に、自分の生まれた場所を紹介する、として歌いだしたのが「東村山音頭」だった。ワンコーラスしかなくて、二番は志村本人が作ってしまったという。
「カラスの勝手でしょ」は、ある高名なTVプロデューサーの発案だったらしい。
「当時、子供たちの間で、ヘンな歌をうたうのがハヤっていて、「カラス」も、その方の娘さんが家で何気なく歌っていたらしいんです。耳にしたそのプロデューサーが、あ、それは使える、と『全員集合』のスタッフに教えてくれたんですね」
最後に、やはり数多くのヒットギャグがうまれた『みごろ!食べごろ!笑いごろ!』については、
「けっこう勘違いされるんですが、電線音頭にしても、小松の親分さんにしても、あれは基本的に台本の通りです。アドリブから出たものではない。キャンディーズをはじめ、若いコもたくさん出ているし、アドリブの余地はほとんどありませんでしたね」
伊東四朗も小松政夫も、ほぼ台本の通りにやっていたという。
「ただ、伊東さんが、あんな電線音頭なんて、素顔じゃ恥ずかしくてできない。とんでもない格好にしたい、って申し出があって、ベンジャミン伊東に変身することになったんです」
たくさんの「昭和ギャグ」と関わってきた田村さんだが、今も、放送作家界の重鎮として、バリバリ現役続行中だ。
第8回 いま寛大に訊く 2015-01-04
漫才の「寛太寛大」といえば、やはり思い出されるのがヒットギャグ「ちょっと待ってネ」。残念ながらはな寛太さんは3年前にお亡くなりになってしまったが、いま寛大さんは舞台役者として活躍。藤山直美さんが座長をつとめる舞台などに登場し、「ちょっと待ってネ」といえば、客席は大爆笑だ。
その寛大さんに、「ちょっと待ってネ」誕生のキッカケについて、まず聞いてみた。
「ぼくら、もともと二人とも松竹新喜劇で芝居してたんですが、なかなか役もつかないし、だったら漫才やってみようか、と組んだんです。で、東京に出ていって、浅草の木馬館で月に10日出さしてもらって、残りの20日は、東北や、関東のストリップ劇場を回ってネタをやってたんです」
昭和43年の結成だから、約40年前のこと。その結成1年目に回った中で、横浜セントラル劇場というストリップ小屋もあった。
踊り子さんのショーの合間に登場した寛太寛大さん。持ち時間は20分。それが終わるころには舞台袖で次の踊り子さんがスタンバイしていてバトンタッチする手はずになっていた。ところがある日、そろそろネタも終わろうという頃になっても、袖の踊り子さんがいない。出番を忘れているらしい。
あわてたのは、舞台上の二人。まだ漫才を始めたばかりで、ネタを自由自在に延ばすようなテクニックはない。仕方なく、舞台から楽屋に向かって、「おねーさん、出番でっせ」とマジに声をかける。すると、楽屋にいたその踊り子さんも出番に気付いて、大声で、
「ちょっと待ってネ!」
これが客席にもろに聞こえて、お客さんが大爆笑。さっそく二人も、「あれは、おもしろそうやな」となってネタで使い始めたのだという。それも、今流行の歌をうたいつつ、その間に「ちょっと待ってネ」を入れる、という形でアレンジを加えつつ。
「ウケましたね。あちこちのストリップ劇場回って、ずっとウケてました」
45年に大阪に戻ってからはテレビ番組の出演も多くなり、レギュラーで出演した毎日放送『夜の大作戦』では、とんでもないことまで起きている。
「何と、あの初代ジェームス・ボンド役のショーン・コネリーに、「ちょっと待ってネ」をやってもらったんです」
『夜の大作戦は』はコントを中心としたバラエティ番組で、オープニングコントには、由利徹をはじめ、一流コメディアンがたくさん登場する。そして、ある回には、映画の宣伝にやってきたショーン・コネリーも出演した。
さっそく局側がコントを考えた。レギュラーのお笑いメンバーが悪役で、センターから出てきたコネリーが機関銃を撃つと、悪い奴らはみんな倒れる。そしてコネリーが最後に一言。「チョットマッテネ」。
だが、リハーサルでそれを見た映画配給会社の社員は難色を示す。「まさか、こんなギャグをジェームス・ボンドにはいわせられません」と。それに対して番組プロデューサーは
「だったら、出演せずに帰ってもらってけっこう」
寛大さんによれば、
「結局、ショーン・コネリー、本番でもやってくれました。映画会社の人も折れたんでしょうな。もちろん大爆笑でした」
それから40年近くたった今でも、このギャグは生きている。
「(藤山)直美さんのお芝居でも、ご本人から、「あのギャグは、絶対に入れな、あかんよ」といわれてます」
これほどの大ヒットギャグを持っていながら、寛大さんは、「ぼくらはギャグ頼みの漫才は嫌い。しゃべくりでウケるコンビを目指してきました」と語る。とはいえ、今でも、舞台で「ちょっと待ってネ」をいえばドッとウケてしまうのだから、これは一生の財産というしかない。
第7回 永峰明に訊く 2014-12-02
かつて、フジテレビのディレクターとして、プロデューサー横澤彪のもと、『THE MANZAI』『オレたちひょうきん族』などの数々のバラエティ番組を手掛けた永峰明さん。現在はフジテレビを退社し、フリーの演出家として、またクリエーター集団を率いる代表として、放送業界のみならず、舞台、出版など、様々な分野で活躍している。
その永峰さんに、番組作りの現場で見たヒットギャグ誕生の瞬間、あるいはギャグを生みだすための芸人たちの苦闘の様子などを、以前、語ってもらったことがある。
「『THE MANZAI』でヒットしたギャグは、だいたいみんな、その前からやっていたようなもので、ぼくらが一緒に考えたわけではありません」
たとえば、B&Bの「もみじまんじゅー」、ざ・ぼんちの「おさむちゃんでーす」、ツービートの「赤信号 みんなで渡れば 怖くない」、紳助竜介の「オレ、体弱いねん」といったギャグは、永峰さんの記憶によれば、昭和55年4月の第一回放送ですでにやっていたという。
すでに出演者全員が長い下積みを経ており、そこで積み重ねたネタやギャグがあふれて飛び出しそうな状態だったのだ。第二回から登場ののりお・よしおも、すぐに「ツクツクボーシ」などはやっていたという。
「ただ、控室では、「あのギャグはウケがいいから、多用したらいいよ」などとディレクターたちが演者にアドバイスしたりしましたね」
観客は、各大学の放送研究会やマスコミ研究会などに集めてもらった大学生たち。ギャグに対する反応も素早い。
ギャグに対する姿勢でも、いろいろあって、たとえばツービートや紳助・竜介は、掛け合いが中心でフレーズのギャグにはあまり頼らない。ざ・ぼんちは、会話の中に流行語になりそうなフレーズを織り込んでいく。ところが、のりお・よしおののりおは、脈絡もなく、いきなり放つ。
「彼はテレビのコマーシャル・ネタも多かったんですが、大阪のかまぼこ屋の製品名をいきなりわめきだした時は驚きました」
一方、56年スタートの『ひょうきん族』のギャグは、収録の中で、あるいは楽屋で突発的に生まれ、ヒットしていったものが多いという。
たとえば「タケちゃんマン」のコーナーで生まれたギャグは、ほとんどさんまとたけしとの会話の中から生まれていった。たけしが「お前は関西人だから、パーっていうより、アホだろ」とさんまに言い、何気なくさんまが「アホちゃいまんねん。パーでんねん」と切り返す。それをスタッフが、「いいじゃない、そのフレーズ」と盛り上がって、実際にオンエアに乗せてみたらバカウケした、といったように。
「お二人はとにかく忙しかったですからね。台本をいちいち覚えてもらうほどの時間がない。最初に台本の流れでストーリーを押さえる分は別のタレントさんたちにちゃんと準備しておいていただいて、最後の対決シーンの掛け合いを、お二人に「ご自由にどうぞ」って任せてしまうんです。こちらで追い込んでいけばいくほど、面白いフレーズが出てくる」
いわば、「狙って作ったギャグ」ではなく、「その場の空気の中から生まれるギャグ」。
「ぼくらは『ひょうきん族』では、自然発生的な笑いをめざしていたんです。ちょっとテンションが高めの日常会話でいこうと考えていた。だから、今でも、そこから生まれたギャグは普通に合コンで出しても通用します。「ガチョーン」だと強烈すぎるでしょ。なかなか空気に合わない。でも、「アホちゃいまんねん、パーでんねん」だったら、会話の中でもちよっとしたアクセントとして使えます」
かつて「お笑い芸人」と呼ばれていたタイプがほとんど消滅し、今、テレビでは、一般人より日常を面白く語れる「お笑いタレント」が全盛の時代になっている。永峰さんの話を聞いていると、ちょうどその変換点あたりに『ひょうきん族』が位置していたことが、何となくわかる。
第6回 堺すすむに訊く 2014-10-29
堺すすむさんといえば、言わずと知れた「なーんでかフラメンコ」。昭和生まれのギャグでありながら、現在でも『笑点』や『笑いがいちばん』などに出演する時には、この「なーんでか」ギャグを披露するために、子供たちまでよく知っている。
インタビューでお会いした時点で、すでに60代も半ば過ぎのはずなのに、見た目が非常に若い。40代といっても通るくらい。
「大阪で活動していたぼくが、東京に出てきたのは昭和38年」
そう言われて、初めて、「あ。けっこうお年なんだな」と気付く。
もともと大阪でもモノマネ芸人としてデビューしていた堺さんは、東京に移ってからもモノマネを表芸にしていた。一曲の中に何人もの歌手のモノマネを入れる構成などは、堺さんが元祖といってもいい。また、森進一のモノマネなども、堺さんが作ったスタイルを原型にして、後のモノマネ芸人がいろいろアレンジして広がったといえる。
昭和50年スタートの視聴者参加番組『歌まね振りまねスターに挑戦』では、審査員として登場し、海外旅行を獲得する出演者がない時に放った言葉、「今週は、なーい」がヒットギャグとして脚光を浴びる。
「その時の成功もあって、何かハヤリ言葉を作ってみたいな、と思うようになったんです。それも、今までみたいにこちら側からの一方通行じゃなく、見ている皆さんも参加できるようなものはないかな、と」
ちょうど名古屋で、『エバラ歌謡大作戦』という番組にレギュラー出演していた。そこで、スタッフとして出入りしている若者たちを集めて、「なぞなぞ」を作ってもらうことにしたのだ。舞台上の芸人がなぞなぞを出し、観客に答えてもらったら面白いのではないか、と考えたわけだ。
しかも、そこにメロディーを乗せて、決め手になる言葉を入れたい。浮かんだ言葉が、「なーんでか」だった。
たとえば「アンパン、ジャムパン、食パンが歩いている。メロンパンが後ろから声をかけたら食パンだけが振りかえった」。そこで「なーんでか」と入れて、お客さんに考えてもらう。答えは「食パンには耳がある」。まさになぞなぞなのだ。
「昭和50年代の半ばくらいでしょうか。確か東海テレビのモノマネのコーナーで最初に試したんだと思います」
その頃は、『スケーターズワルツ』でやったり、タンゴでやったり、乗せるメロディーは固定していなかったらしい。が、なかなかシックリいかず、フラメンコにしたら、どんなに前振りの尺が長くても強引に入れられるので、「これでいこう」と決定する。
ただ、ウケなかった。3年間はスベりまくっていたという。ステージで「なーんでか」を試したくてもなかなかウケず、結局はモノマネ中心でやるしかないことも多かったという。
「わからないんですよ。3年くらいたった頃に、突然ウケだした。特に子供たちが喜んでくれる。お陰でNHKからレギュラーの仕事が来たし、どの番組に出てもモノマネよりも「なーんでか」でいってくれ、といわれるようになったんです」
普通、3年もスベッたネタは、なかなか執着しない。だが堺さんは「自分が面白いと思っていたから、ウケなくてもやりたかった」と平然と語る。
しかし、その3年間は決して無駄にはならなかった。ウケなくてもウケなくても、毎日、ネタを考え続けていたために、ウケ出した頃には千個を超えるストックができていたのだ。
「テレビで、一回10本から30本くらい使うんですが、そのストックと、新しいネタを組み合わせればいくらでもやれます」
「なーんでかフラメンコ」が表芸になってしまった堺さん。そのために、たとえば飲みに行って、遊びのつもりでモノマネを披露したりすると、若い人から「堺さん、モノマネもうまいんですね。今度、モノマネ番組に出てみたら」といわれるようになったとか。
出演だけではなく、最近は、演芸番組の企画構成や、若手お笑い芸人の育成まで手掛けているという堺さん。昭和から平成と、ずっと生き続けた不滅のギャグ「なーんでか」はまだまだやり続けると誓っていた。
第5回 橋達也に訊く 2014-10-06
かつて、昭和40年代、「ストレートコンビ」という二人組がいた。激しいアクションとテンポのいい掛け合いで人気を呼び、中でも、両手を万歳させてフラフラと動かしながらの「だめなのねー、だめなのよー」と叫ぶギャグと、「千葉の女は乳搾り!」という二つのギャグがウケにウケた。
日本喜劇人協会会長もされていた橋達也さんは、そのストレートコンビの「片割れ」であった。橋さんにお話しを聞いたのは浅草。橋さんが座長をつとめる「浅草21世紀」公演の終了後で、会場の木馬亭は、平日昼間でも、150席は満員。月に一週間の割で、今も公演を続けている。お話を伺った時も、満員だった。いつもこんなにお客さんが入っているのか聞くと、
「まだきょうは少ない方。土日には補助席も出す」
どうやら、浅草のお笑いはも近年、相当盛り上がっているようだ。
さて、話はストレートコンビ時代のことに。
相方の花かおるさんと出会ったのは、新宿ミュージックというストリップ劇場でコメディアン修業をしていた時のことだ。渥美清の浅草フランス座の例を出すまでもなく、昭和20年代から40年代あたりまで、ストリップ劇場は、いわばコメディアン予備軍にとっての「学校」の役割を果たしていた。そこで、女性の裸目当てに来ている観客を笑わせなくてはいけないという厳しい環境の中で、演技も、アドリブも、鍛えられていくわけだ。
昭和43年、その舞台で一緒だった花さんから、突然、「相談に乗ってくれ」との連絡がある。コンビ結成の誘いだった。
時はまさにコント55号が爆発的な人気を誇っていたころ。テレビ画面をはみ出るアクションが売りの55号が売れるなら、自分たちにもチャンスはある、と説得されたのだ。
橋さんも応じて、すぐに作ったネタが「ソルジャー部隊」。花さんがソルジャー部隊の教官で、ソルジャーの橋さんに、機関銃の打ち方や負傷兵の助け方などを教える。で、うまくできない橋さんをこずいたり、倒したりするうちに派手なアクションになる。
この、たった一本のネタをもって、はじめてテレビ番組に出演した。で、そこで、ついネタが詰まった時、橋さんがとっさに出したのが「だめなのねー、だめなのよー」だった。
結果はバカウケ。トントン拍子にレギュラー番組が決まる。テレビ東京の『爆笑チャンネル』だった。
ここでまた、橋さんが整体師、花さんが患者役のコントをやる際、休憩中に、何げなく橋さんの頭にフッと浮かんだ言葉が「千葉の女は乳搾り」だった。つい口に出すと、他の出演者たちも、「それ、面白いんじゃない?」と上々の反応で、本番でもやってみたら、予想通りウケる。橋さんによると、
「学生時代、アルバイトで千葉に行って屋根ふきをやっていたことがあったんです。瓦かついで屋根に上がると、ちょうど前が小さな牧場で、中年のオバサンが牛の乳を搾っていた。へー、千葉の女は乳搾りか、とその光景が頭に残ってたんですね」
この二つのヒットギャグをひっさげて、一時は先行するコント55号に肉薄しそうな時期もあった。だが、テレビ出演より、お金になる地方やキャバレーでの営業などを重視する事務所の方針もあって、なかなか次への飛躍ができない。結局、昭和49年に解散。
その後、橋さんはピンでの活動、「橋達也と笑いの園」というお笑いユニットでの活動を経て、現在に至っている。
「浅草21世紀は、投げ出さなくてよかったと思ってますよ。はじめの頃は入りも厳しくて、浅草でこんなことやってても客なんか来ない、と諦めかけたことが何回もあります」
そんな橋さんの尽力もあって、浅草のお笑いは復興に向かっている。だが、残念ながら、当の橋さんは平成24年、74歳にしてこの世を去っている。
第4回 牧伸二に訊く 2014-09-02
『大正テレビ寄席』(昭和38年スタート)の司会者として15年間にわたって日曜昼の主役をつとめた牧伸二さん。平成25年に、突然自ら命を絶つという衝撃的な最後を迎えた方だったが、私も一度だけお話を伺ったことがあった。
インタビューのために伺った浅草・東洋館は、平日の昼間にも関わらず、中高年の観客を中心に200人以上は入る会場がほぼ満杯。ウクレレを持って「あー、やんなっちゃった」と歌う「やんなっちゃった節」で、某政治家の資金疑惑をネタにするなどの社会批評を繰り広げ、笑いをとっていた。
「ぼくは、「今」のことしかしゃべらない」
ネタでは決して過去を振り返らないのが牧さんのポリシーだった。
牧さんといえば、ウクレレがつきものなのだが、ウクレレを持つようになったのは、昭和30年代半ばのこと。
「それまで、立ってしゃべるだけの漫談をやっていたんですが、師匠の牧野周一に『どうも地味だな。楽器をもってやったらどうだ』といわれたんです。でも、三味線やギターやアコーディオンは、もう使っている人がいる。だったらウクレレがいなかったし、値段も安いからいいだろう、と決めたんです」
当時でも格安の700円のオモチャのようなウクレレを買う。音も悪いし、もともと、触ったこともないのだから、うまく弾けない。それで、つい口ずさんだフレーズが「あーやんなっちゃった」。
弾けなくてはしょうがないので、ウクレレの教則本を買ってきて、さっそく練習した曲がハワイアンの「タフア・フアイ」。3コードだけ押さえられれば演奏できる手軽さにひかれて練習しているうちに、いつの間にか、この曲が「やんなっちゃった節」の原曲となっていった。
「『タフア・フアイ』の最初が、「あー」というため息だったんです。それで「あー、やんなっちゃった」とうまくつながった」
最初は「やんなっちゃった」を二回繰り返していたのが、どうもうまくハマらなくて、うしろの部分を「あー、驚いた」に変えていったという。
「やんなっちゃった節」がヒットしたキッカケは『大正テレビ寄席』だろう、と思い込んでいる向きも多いだろうが、実はラジオだったのだ。昭和35年に文化放送の『ウクレレ週刊誌』というレギュラーを持ち、そこですでに「やんなっちゃった」は人気になっていた。
「歌は売れていても、ラジオですから顔は知られていないわけですよ。だから、キャバレーの営業で呼ばれてウクレレ持っていくと、バンドマンの部屋に連れて行かれるんですよ。それでみんな、『牧伸二が来ない。どうした』ってよく騒がれました」
もちろん『大正テレビ寄席』が始まるころには、顔も売れ、そんな経験は一切なくなったが。
また、この時代は、キャバレーの全盛時代で、お笑い芸人といえば、売れている人たちも、若手も、みんなキャバレーの舞台で稼いでいたという。
「忙しい時は1日に4~5軒の掛けもちは当たり前でした。新宿あたりで、向こうから時代劇の衣装着たまま走ってる3人組を見たらてんぷくトリオで、こっちも衣装のままで『お互い、大変だね』といってすれ違ったこともありました」
売れっ子ともなると、テレビの仕事もあってなかなか時間通りには始められない。店の方も忙しいのはわかっていて、30分くらい遅れても文句はいわなかったらしい。
『大正テレビ寄席』の時代と、平成の時代とで、お笑い界はどう変わったと思うか、牧さんに質問してみると、
「昔を懐かしがるわけではないが、芸人の基礎は、昔の人たちの方が出来ていたと思いますね。たとえばコントにしても、昔は、芝居でみっちり鍛えていた人がコントをやるから面白かったし、サマになっていた。師匠にどなられたり、先輩に教わったり、そういうことが積み重なっていたし。チャンバラのコントやる人なら、着物の着方、帯の締め方も全部わかってるわけです。今は、そういう修業をしてないからね。ただ、昔からやってる連中も、もう自分らの出る時代じゃないと思わず、もっともっと前に出て行かなくちゃいけないですよ」
建設的な話をたっぷりしていたのに、なぜああいう最後を選んだのか、いまだによくわからない。
第3回 せんだみつおに訊く 2014-08-19
・ 昭和のテレビ・バラエティが生んだスーパースターは数多くいるにせよ、せんだみつおさんもその代表的な一人なのは、誰も異論はなかろう。
昭和47年スタートの『ぎんざNOW』の司会をきっかけにその快進撃は始まり、『うわさのチャンネル!』『せんみつ湯原のドット30!』などで、50年代前半のテレビ界を席巻していった。
その間に生まれたヒットギャグも数多く、特に「ナハナハ!」や「せんだ、エラい!」などは、確実に当時、テレビの前にいた昭和30年代生まれの人々には忘れられないフレーズになっていることだろう。
「ぼくはね、だから「ナハナハ」は、「アイーン」「コマネチ!」と並ぶ昭和三大ギャグだって前から言ってるんです」
と勢いよく話し始めてくれたせんださん。
「あ、別格として「アジャパー」もあったか」
とつぶやきつつ、彼独特のギャグ論を語っていく。
「ギャグって、小道具なんですね。別にそれをずっと言い続けていても面白いわけがない。一回、ポイントを作るために使うカンフル剤というか、切り込み隊長みたいなもの。ま、ないよりはあった方がいいが、頼りすぎはいけない」
さらに、ギャグは、なるべくなら「意味ない言葉」をぶつける方がいいのでは、と考えているようだ。
「昔の、藤田まことさんの「耳の穴から手つっこんで奥歯ガタガタいわしたる」っていうのでも、意味がわかるようで、よくわからないでしょ。バカバカしくて、おふざけの極みみたいなものの方がいいわけですよ。だって、前後の話の流れなんて関係なく、そこだけ見ても笑ってもらえる」
感覚がテレビ的なのだ。チャンネルが回ってきた瞬間に面白くなければ、また別のチャンネルに変えられてしまう。だったら、瞬間でもアピールできるギャグをカマす。「刹那的で結構。それがテレビ」というわけだ。
「ナハナハ!」も「せんだ、エラい!」も実はアイデアを考えたのはせんださん本人ではなく、『ドット30!』の相方・湯原昌幸だったとか。
「ウルトラマンが着地する時、「ナハ」っていう。あれ、使えるんじゃない、となったんですよ」
それがどんどん膨らんでいき、あの手をかざして振る独特のアクションもできた。
「ウルトラマンは78星雲から来ているからナハナハだ、とか、七転び八起きでナハナハだから縁起がいいとか、いろいろ後付けしてきました。ただ、あとで本当は87星雲だったってわかったけど」
「せんだ、エラい!」の方はモデルはなく、純粋に湯原のオリジナルだった。
「ナハナハは、今でもたくさん使いようがあるギャグなんですがね。たとえばテレビの天気予報で、『沖縄の那覇では』を、『沖縄のナハナハでは』と言ってくれるだけで復活できる。ぜひやってほしい」
平成も20年以上があった今でも、ヒットギャグの再浮上を虎視眈々と狙っているあたりが、いかにもせんださんらしい。
第2回 澤田隆治に訊く 2014-08-04
昭和30年代から40年代にかけて、朝日放送のディレクターとして『スチャラカ社員』『てなもんや三度笠』などの爆発的ヒット番組を作った「お笑い界の巨人」澤田隆治さん。さらには50年代にも、『花王名人劇場』のプロデューサーとしても有名で、MANZAIブームの仕掛け人としても知られる。
現在も、自らの発案で創設した「笑いと健康学会」の会長をつとめるほか、若手お笑い芸人の発掘やお笑い番組の制作、ライブのプロデューサーなど縦横無尽の大活躍。見た目もすこぶる元気で、とても昭和8年生まれには見えない。
もちろん「昭和ギャグ」にまつわるエピソードは数知れずお持ちで、その、ごくごく一端を語ってもらうことにした。
「ぼくら、芸人が売れるためには流行語作るのがいいということは、ダイラケ(中田ダイマル・ラケット)で知りました。『ダイラケのびっくり捕物帖』で私がディレクターとして関わったんですが、二人の言った「ゆうてみてみ
聞いてみてみ」「しらんかっとんてん」 は、大阪でムチャクチャハヤりましたからね」
さっそく懐かしい番組名が出てきた。『ダイラケのびっくり捕物帖』とは昭和32年にスタートしたコメディ時代劇。当時、大阪でも人気のあったダイラケが岡っ引きに扮し、森光子も出演していた。さらに、この番組でテレビデビューしたのが藤田まこと。
「ダイラケの場合は、キャッチコピーとして意識してハヤらそうとしてました。そのうち、どんどん言葉が独り歩きして膨らんでいって、もちろんダイラケの名前もどんどん大きくなっていく」
そこで、ヒットギャグの威力をつくづく知った、と振り返る。
「ぼくも、内海突破の「ギョッ」や伴淳三郎の「アジャパー」で育った世代ですから、いわゆる言葉のギャグが芸人の武器になるのは知っていました。でも、身近で、あれだけの大ヒットを見たのは初めてでした」
それから後は、いくつものヒットギャグを身近で見たし、現場で関わってきた澤田さん。
その次に出た思い出に残るヒットギャグといえば、『スチャラカ社員』(昭和36年スタート)で飛び出した「ホーント? ちーともしらなかったワ」だという。
ある会社を舞台にした公開コメディとして人気を集めたこの番組、そこに登場する、やや太り気味の、人見きよしというコメディアンがいた。たとえ仕事で失敗しても責任もとらず、上司の説教も飄々として受け流す中間管理職を演じると、実にウマい。いわば「無責任サラリーマン」の先駆けのような存在。
ただ、惜しいかな、芝居は上手なのだが、もう一つ、インパクトが弱い。そこで澤田さんが考えたのが、かつてダイラケが成功したように、インパクトのあるギャグを与えてあげることだった。
まず、アクションを考えた。アボット&コステロという、「凸凹コンビ」として映画にもたくさん主演したアメリカの二人組がいた。で、そのデブのコステロの方は、ズボンがストンと落ちるギャグを得意としていた。「あ、あれなら、人見きよしに合う」と、まず思いついたのがひとつ。さらにセリフの方だが、ちょうど同じ番組に、頭がつるつるで体のデカい田中淳一というコメディアンも出演していた。その彼の日常での口癖が「ホーント?ちーともしらなかったワ」だったのだ。
「よし、この両方を合わせて彼にやらしてみよう、と決めたんです」
人見扮する課長が、たとえばミヤコ蝶々扮する社長にお説教された時などに、この「ホーント?」と来て、ズボンが落ちるギャグを使ったら、たちまちウケまくり。人見きよしは全国区のコメディアンになり、主演番組まで出来たという。
その人見きよしに代わって入った長門勇の「おえりゃあせんのう」という岡山弁ギャグもまたヒットした。
しかし、澤田さんがディレクターを務めた番組での最大ヒットといえば、やはり『てなもんや三度笠』。その中で、もっとも強烈なギャグといえば、「オレがこんなに強いのも、あたり前田のクラッカー」だろう。
「あの頃は、番組アタマのアバンタイトル作るのが楽しみでね。『てなもんや』の時も、何かそこで最後の決め言葉があるといいなァとは思ってたんです」
辻堂の扉がギーッとあいて、藤田まこと扮するあんかけの時次郎が出てきて、別の出演者との軽い掛け合いがある。そのあと、何か決めの一言がほしい。だが、なかなか決まらないままにビデオ撮りの本番が近付いた時、扉のギーッという音を出す効果マンが何気なく言った言葉が、「オレがこんなに強いのも、あたり前田のクラッカー」だった。
語呂もいいうえに、スポンサーの宣伝にもなる。さっそく、いただいた。
「他にもたくさん思い出に残っているギャグはありますが、インパクトが強かったものといえばルーキー新一の「イヤーン、イヤーン」とか、財津一郎の「キビシーィ」とか、強烈でしたね」
どちらも本人が考えたギャグを番組で使っただけなので、澤田さん自身がギャグの誕生に立ち会ったわけではない。ただ、それぞれに、忘れられない記憶があるという。
ルーキー新一の方でいえば、この「イヤーンイヤーン」は、両手で胸のあたりをつまんで、体を左右に揺らしながら言うのが特徴。だが、ある先輩コメディアンと共演した時、いわば「イジワル」でその先輩は、ルーキーの「イヤーンイヤーン」を封じたという。ルーキーが、手を胸に持ってきた時、咄嗟に「何?
その手は」とツッコンで、「イヤーン」をやらせる「間」を与えなかったのだとか。
「昔はね、そういうイビリが今よりたくさんあったんです。でも、それをはねのけて一流になったから、生き残った連中は強かった」
財津に関して言うと、『てなもんや』の台本を書いていた香川登志緒は、「キビシーィ」と叫びつつ狂乱するような彼のキャラクターが大嫌い。そのため、台本では出るたびに斬られることにして消してしまったのだが、澤田さんはそのたびに復活させた。
「主に関西のコメディアンが、『てなもんや』でギャグを試して、当たると全国区になる図式ができていったんですね。だから、みんな必死でしたよ」
その熱気が、番組を盛り上げた大きな要因にもなったという。
「もともと、大阪にあった漫才という話芸のスタイルを引き継ぎつつ、立体コメディの形を作ったのが『スチャラカ』であり、『てなもんや』であったわけです。そこにはボケ、ツッコミのべースがあって、登場人物たちのキャラクターも、非常にはっきりさせながら進行していく必要があった。だからギャグも必要不可欠だったんです」
そこから生まれたヒットギャグも数多い。ただし、おびただしい数の、「当たらなかったギャグ」もあったという。
「ギャグは当たってなんぼ。当たらないものは忘れてしまいますな」
かつて出演者たちやマネージャーを震え上がらせた「コワモテ・ディレクター」だっただけに、シメの一言はなかなかに厳しいものだった。
第1回 松鶴家千とせに訊く 2014-07-01
「わかるかなァ、わかんねェだろうナ」で、昭和50年前後に一世を風靡した松鶴家千とせさん。
千とせさんとお会いしたのは、ご自身のお宅の最寄り駅に近い喫茶店。初対面の私に、深々と頭を下げて挨拶してくれるような、評判通りの丁寧な人物であった。
「『わかるかなァ、わかんねェだろうナ』ってあの言葉は、もう自然に出てきたんです」
長く、浅草の木馬館という劇場に出ていた千とせさん。しかし、そこは本来は女性たちが登場して安木節を踊るのが売り物で、千とせさんは、あくまでも場つなぎの添え物的要素が強かった。ところが、すでにその頃からアフロでアゴヒゲで、ジャズっぽいメロディーを口ずさむ「バタ臭い」芸風だったのだから、中高年中心のお客さんの層とは合わない。そこを強引にネタを演じつつ、
「ほら、そこのシジィ、オレのネタがわかるか。わかんねェだろうな」
などとやっていたのがはじまりだったという。
「荒っぽかったねェ。お客さんの眼を少しでも向けさせるために、わざとやったところもあるんですよ」
元来、お笑いの世界を目指していたわけではなく、なりたかったのは「ジャズ歌手」。
「満州から引き揚げてきて、私の一家が住んだのが福島県の原町。飛行場があったところで、戦後になると、アメリカ人がいっぱい入ってきたんです。それでラジオ聴くと、よくジャズが流れてました。ルイ・アームストロングとかね。あれ聴いて、カッコいいな、オレもジャズ歌手になりたいな、と思ったんです」
アメリカに行きたい。でもその前に東京に行かなきゃダメだろう。と、ほとんど家出のように上京してきたのが昭和28年。15歳の時だ。
「さっそくジャズの学校に行こうとしたら、まず寝る場所はない。あそこで世話になったら、といわれて、人に紹介されたのが松鶴家千代若・千代菊師匠の家。だから私は、最初は弟子になるつもりじゃなくて、ただ部屋を貸してもらうつもりだったんです」
千代若・千代菊といえば、漫才に民謡を取り入れた独特の芸風で、すでに人気が高かった。だが、千とせさんは知らなかった。いわば心ならずも、そこではじめて漫才をはじめとした「お笑い」と、そこで初めて本格的に接触したわけだ。自然に、師匠の付き人として寄席に出入りしたりするようにもなるが、ジャズ歌手の夢は簡単に捨てたわけではなかった。
「いずれアメリカに行くのなら、何か手に職をつけた方がいいな、と理容師の資格をとったりしてましたから」
芸歴10年を超えたあたりからは、「アメリカかぶれ」といわれようと、気にせず、独自のファッションを考えて舞台にも上がった。自分で割りばしを使ってパーマをかけ、アフロにサングラス、あごヒゲで寄席にも出た。周囲からは「バカヤロー」と怒られても、あえて押し通した。
ようやく「わかるかなァ」で売れ出したのが昭和48年ころ。実に入門から20年がたっていたのだ。結局、アメリカでジャズを勉強することはできなかったが、日本で、「夕焼け小焼け」などをジャズ風メルヘンにしてヒットさせたことで、夢の一部は実現した。
芸能活動のかたわら、ボランティア・グループ「さつまいもの会」を結成し、刑務所や介護施設などへの慰問活動を始めた。
「昔、木馬館の人たちについていって、刑務所に慰問に行ったことがあったんです。それで『夕焼け小焼け』を歌ったりしたら、それだけで囚人の皆さんが泣き出してしまってね。私ももらい泣きですよ。みんな、故郷を思い出したんでしょうか。私の芸でこれだけ感動してくださるんなら、と思ってその後もやっているんです」
心やさしい人なのだ。